天然ふーふ
持続可能な自給自足的暮らしを求めて、東京から瀬戸内海沿岸に移住(いわゆるIターン?)した我が家(または僕)の生活や思いを綴るブログ。3.11の地震による原発事故後、これまで自分たちが送ってきた生活のあり方を考え直して移住を決意。移住後は、これまでの文明的な生活は否定せずとも、できるだけ電力会社や石油エネルギーに「依存」することから脱却し、持続可能な社会やコミュニティ、生活を作ることを目指す。もちろん原発は必要ないと思う。現在、冷蔵庫なしで低電力生活中。月の電気代は500円ほど。
2012
November 26
November 26
24日(土)に尾道のゲストハウス「あなごのねどこ」で開かれた伊藤洋志さんという方のトークイベントに行ってきました。ここ5年あまり彼が実践しているナリワイ(生業)の紹介とプチ・ワークショップという内容で、とても楽しい時間でした。
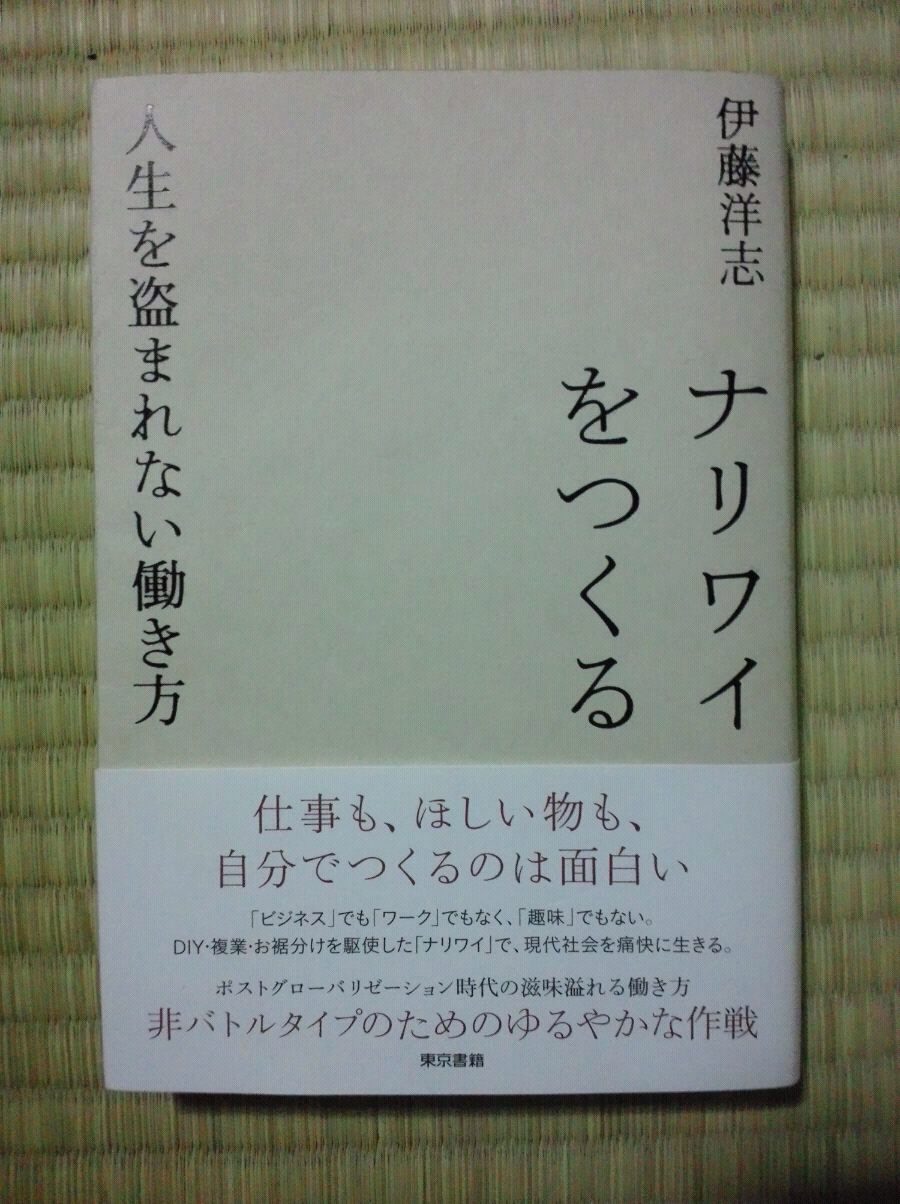
『ナリワイをつくる 人生を盗まれない働き方』伊藤洋志さん 著
『ナリワイをつくる 人生を盗まれない働き方』伊藤洋志さん 著
このイベント、尾道在住の友達が企画していて、「西村佳哲さん好きな二人(僕と妻)にはぜひ来てほしいと思ってた」と言われてました。
人生・生き方にとって、どう仕事するか、どう仕事と関わっていくかはとても重要な問題です。答えは一つではないし、必ずしも働いている全員がそれぞれ満足いく答えに基づいた仕事をしているわけではないと思いますが、僕と妻は自分たちなりによい答えを見つけることにまだまだこだわっているのです。
【ナリワイとは】
伊藤さんが言う「ナリワイ」とは、個人がそれぞれに営む小さな事業のようなものです。彼自身のナリワイとしては「モンゴル武者修行ツアー」の敢行、「田舎で土窯パン屋を開く講座」の取次、「木造校舎で結婚式」のプランナーなどなどがあります。漢字の「生業」とほぼ同じと言ってました。西村佳哲さんの話によれば、仕事の規模は「はたらき→生業→事業→産業」のような順番で大きくなり、大きくなるにつれて個人の範疇を離れていく傾向にあるようです。「生業」は「はたらき」(本人の自然性のようなもの)の次で、個人を大きく疎外はしない規模の仕事ということになります。これぐらいの規模の仕事をいくつか営みながら自分らしく生きることについて話を聞くのが今回のイベントの主旨でした。
【専業的な仕事=生き方という認識】
一般的に、よく知らない人のことを知ろうとする時だいたい職業を聞くと思います。答える側は普通「IT企業に勤めてます」とか「農家です」といった感じで答えると思いますが、現代に生きる僕らは「専業的な仕事を持っている人=ちゃんとした人」という考え方にとらわれすぎているのではないでしょうか。伊藤さんはこれからの働き方として、いくつかのナリワイを組み合わせて生きていくことを提唱しています。
【歴史的に見ると現代は異常に非DIYな時代?】
一人の人間が一つの仕事を専業的に行うというのが一般的になったのは戦後の高度経済成長期らしく、それまではもう少し生活に根ざしたいくつかの仕事をしながら人々は生活していたようです。たとえば今だと自分の家の床の修繕を専門の業者に頼んだりしますが、昔は各家庭で自分でやるのが普通だったとか。味噌の仕込みや梅干し漬けなども最近の家庭ではあまりやらないと思いますが、昔はどの家庭でもやってたのではないでしょうか。ナリワイは生活を自給する行為から生まれることが多いそうで、こういった失われつつあるDIYな行為の中に多くのヒントが隠されているのではないかと思います。
【生業を行う時間がない】
現代では各家庭において生業を行う時間を意識せず生活しているのではないかと思います。例えば僕は、会社は仕事する空間、家はごはんを食べたり風呂に入ったりDVDを見たりする癒やし&娯楽の空間、というように、無意識に両者を異なる種類の場所であると認識して暮らしていた気がします。家は癒やし&娯楽の空間なので、仕事的な営みである「生業」を行う時間などあえて設けないし、「生業」を意識したこともあまりありませんでした。
【ナリワイは楽しい】
伊藤さんによると無駄な支出を削減する営みの中から楽しみを見つけてそれがナリワイになる、というパターンがよくあるらしいですが、楽しいからこそナリワイになるとも言えると思います。僕の経験上、一般的な「職業」で上意下達の命令的な業務を行う時はまったく楽しくなく、やってる意味さえ見いだせないこともありました。ナリワイは結果や顧客満足度など先のほうにあるものを最重視するというわけではなく、手元で行う作業などの過程も楽しみつつできる営みであることが重要で、だからこそ自主的に続けられるのだと思います。
【それで暮らしていけるの?】
普通に考えて最も重要な点だと思いますが、例えば「年収400万はないと暮らしていけない」というように年収の金額ベースで生活を考えている場合には向かない生き方なのではないかと思います。というか僕はまだ実践できてないので実感としては分かりませんが。ただ、伊藤さんのように「ナリワイの組み合わせ」を専業?とはせず、例えば会社員をやりつついくつかのナリワイを持って生きていくという方法でもよいのではないかと思います。それを許容してくれる会社がどれくらいあるかは分かりませんが。
【イベントの感想】
肩肘張る感じがほとんどなくて、「そこのあなた」的なフリをされても全然緊張しませんでした。伊藤さんの楽しげなキャラが話の内容とマッチしていてとてもよかったです。
人生・生き方にとって、どう仕事するか、どう仕事と関わっていくかはとても重要な問題です。答えは一つではないし、必ずしも働いている全員がそれぞれ満足いく答えに基づいた仕事をしているわけではないと思いますが、僕と妻は自分たちなりによい答えを見つけることにまだまだこだわっているのです。
【ナリワイとは】
伊藤さんが言う「ナリワイ」とは、個人がそれぞれに営む小さな事業のようなものです。彼自身のナリワイとしては「モンゴル武者修行ツアー」の敢行、「田舎で土窯パン屋を開く講座」の取次、「木造校舎で結婚式」のプランナーなどなどがあります。漢字の「生業」とほぼ同じと言ってました。西村佳哲さんの話によれば、仕事の規模は「はたらき→生業→事業→産業」のような順番で大きくなり、大きくなるにつれて個人の範疇を離れていく傾向にあるようです。「生業」は「はたらき」(本人の自然性のようなもの)の次で、個人を大きく疎外はしない規模の仕事ということになります。これぐらいの規模の仕事をいくつか営みながら自分らしく生きることについて話を聞くのが今回のイベントの主旨でした。
【専業的な仕事=生き方という認識】
一般的に、よく知らない人のことを知ろうとする時だいたい職業を聞くと思います。答える側は普通「IT企業に勤めてます」とか「農家です」といった感じで答えると思いますが、現代に生きる僕らは「専業的な仕事を持っている人=ちゃんとした人」という考え方にとらわれすぎているのではないでしょうか。伊藤さんはこれからの働き方として、いくつかのナリワイを組み合わせて生きていくことを提唱しています。
【歴史的に見ると現代は異常に非DIYな時代?】
一人の人間が一つの仕事を専業的に行うというのが一般的になったのは戦後の高度経済成長期らしく、それまではもう少し生活に根ざしたいくつかの仕事をしながら人々は生活していたようです。たとえば今だと自分の家の床の修繕を専門の業者に頼んだりしますが、昔は各家庭で自分でやるのが普通だったとか。味噌の仕込みや梅干し漬けなども最近の家庭ではあまりやらないと思いますが、昔はどの家庭でもやってたのではないでしょうか。ナリワイは生活を自給する行為から生まれることが多いそうで、こういった失われつつあるDIYな行為の中に多くのヒントが隠されているのではないかと思います。
【生業を行う時間がない】
現代では各家庭において生業を行う時間を意識せず生活しているのではないかと思います。例えば僕は、会社は仕事する空間、家はごはんを食べたり風呂に入ったりDVDを見たりする癒やし&娯楽の空間、というように、無意識に両者を異なる種類の場所であると認識して暮らしていた気がします。家は癒やし&娯楽の空間なので、仕事的な営みである「生業」を行う時間などあえて設けないし、「生業」を意識したこともあまりありませんでした。
【ナリワイは楽しい】
伊藤さんによると無駄な支出を削減する営みの中から楽しみを見つけてそれがナリワイになる、というパターンがよくあるらしいですが、楽しいからこそナリワイになるとも言えると思います。僕の経験上、一般的な「職業」で上意下達の命令的な業務を行う時はまったく楽しくなく、やってる意味さえ見いだせないこともありました。ナリワイは結果や顧客満足度など先のほうにあるものを最重視するというわけではなく、手元で行う作業などの過程も楽しみつつできる営みであることが重要で、だからこそ自主的に続けられるのだと思います。
【それで暮らしていけるの?】
普通に考えて最も重要な点だと思いますが、例えば「年収400万はないと暮らしていけない」というように年収の金額ベースで生活を考えている場合には向かない生き方なのではないかと思います。というか僕はまだ実践できてないので実感としては分かりませんが。ただ、伊藤さんのように「ナリワイの組み合わせ」を専業?とはせず、例えば会社員をやりつついくつかのナリワイを持って生きていくという方法でもよいのではないかと思います。それを許容してくれる会社がどれくらいあるかは分かりませんが。
【イベントの感想】
肩肘張る感じがほとんどなくて、「そこのあなた」的なフリをされても全然緊張しませんでした。伊藤さんの楽しげなキャラが話の内容とマッチしていてとてもよかったです。
PR
