天然ふーふ
持続可能な自給自足的暮らしを求めて、東京から瀬戸内海沿岸に移住(いわゆるIターン?)した我が家(または僕)の生活や思いを綴るブログ。3.11の地震による原発事故後、これまで自分たちが送ってきた生活のあり方を考え直して移住を決意。移住後は、これまでの文明的な生活は否定せずとも、できるだけ電力会社や石油エネルギーに「依存」することから脱却し、持続可能な社会やコミュニティ、生活を作ることを目指す。もちろん原発は必要ないと思う。現在、冷蔵庫なしで低電力生活中。月の電気代は500円ほど。
2012
June 05
June 05
6月5日の経路
『北の国から』めぐり(麓郷→富良野市内)
あかなら:『'95 秘密』で使われた「北時計」跡の建物を再利用したお店。
↓
五郎の石の家:テレビのスペシャル番組でおなじみ、黒板五郎の家。
↓
拾ってきた家:雪子おばさん(竹下景子)の家や中ちゃん(地井武雄)の娘夫妻の家が並ぶ「もうすぐ町」の一角。
↓
北の国から資料館:「北の国からパスポート」に押す「三日月食堂」のスタンプが目的。
-- 『北の国から』めぐりはここまで --
↓
neu.spoon!(ノイスプーン):この日は休みだった・・・。
↓
Shimba' Cafe:札幌のフォーラムで知り合った方に教えてもらったカフェ。
↓
アスペルジュ:結婚式後に妻+妻の両親で旅行した際に行こうと思っていたけど行けなかったレストラン。
富良野の宿に泊まり、朝10時ぐらいに出発。『北の国から'95 秘密』で純とシュウが人に知られたくない過去について心の内を話した「北時計」という喫茶店があったのですが、2010年に閉店して、現在はボランティアによって運営されている「あかなら」を訪問。僕たちが2009年に訪れたときは「北時計」でしたが、「あかなら」になって店内の雰囲気も少し変わったようでした。ただ、流れる時間のゆっくりさは変わっていなかった気がしてなんかほっとしました。

あかならの外観
あかならの次はおなじみ「五郎の石の家」を訪問。見物客用の駐車場にレンタカーを停めて石の家に向かう途中、近くを流れる沢の石の上にヘビが!実は嫁さんヘビが生理的に苦手で、見るだけで身の毛もよだつほど。見ないようにして離れました。でも後から思い返すとヘビはのーんびりした様子で、石の上で身体をのばしてひなたぼっこしてたように思います。残念ながら写真には収められていませんが、嫁さんいわく「世の中あんなヘビばっかりだったらこんなに怖がるようにはなってなかったと思う」。石の家は、前回訪問時よりも草が伸び放題、羊もいなくてちょっとさびしかったですが、相変わらずすばらしい家。30分ぐらい何をするでもなく滞在しましたが、その間なぜか「スズメバチに刺されたらいやだ」とか「いま熊が出たら死ぬな」などと考えていました。自然の中に立ってみるとそんなこと考えるもんなんですかねぇ。

五郎の石の家
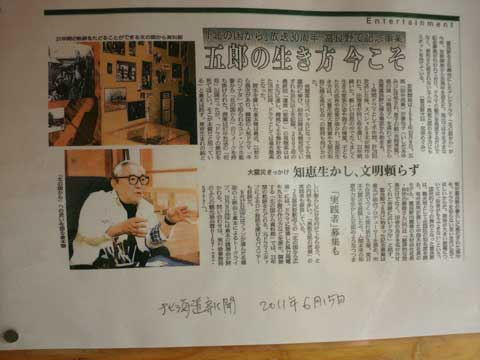
「五郎の生き方 今こそ」と新聞の切り抜きが貼ってありました
「拾ってきた家」は石の家から車で5分ぐらい。すべて廃材などを再利用して作った住宅が立ち並び、今後の僕ら夫婦の生活にはとても参考になります。

純と結の家 ※テレビでは登場していません

雪子おばさんの家。一人なのに広い!
それから富良野市内に戻り、北の国から資料館で三日月食堂のスタンプをもらう。「北の国から」の撮影場所でスタンプをもらえる場所があり、前回訪問時に三日月食堂以外は全てもらっていたのですが、今回、三日月食堂が閉店してしまっていて資料館でもらいました。
そこから札幌のフォーラムで知り合った方の絵が飾ってある「neu.spoon!(ノイスプーン)」という中富良野にあるお店を目指して出発。カーナビと地図でようやく見つけましたが、この日はお休みでした。。
その後は6月5日の宿泊先となっている旭川へ向かって寄り道する感じで再出発。途中、またも札幌のフォーラムで知り合った方に嫁さんが教えてもらった「Shimba' Cafe」というカフェに立ち寄ってひと息。間取りから建物の感じまでとても落ち着く、それでいておしゃれなお店でした。どこかおばあちゃんの家のような錯覚を覚えました。

Shimba' Cafe
この日の夕食は、美瑛にあるレストラン「アスペルジュ」で、美瑛の食材で作ったコースを堪能。実は今回、妻が「おしごと9年半おつかれディナー」としてごちそうしてくれました。「前に行けなかったから行こうよ」的なノリだったのですが、なんとびっくり。ありがとう。これからもよろしく。

嫁さんからのメッセージ
夫
『北の国から』めぐり(麓郷→富良野市内)
あかなら:『'95 秘密』で使われた「北時計」跡の建物を再利用したお店。
↓
五郎の石の家:テレビのスペシャル番組でおなじみ、黒板五郎の家。
↓
拾ってきた家:雪子おばさん(竹下景子)の家や中ちゃん(地井武雄)の娘夫妻の家が並ぶ「もうすぐ町」の一角。
↓
北の国から資料館:「北の国からパスポート」に押す「三日月食堂」のスタンプが目的。
-- 『北の国から』めぐりはここまで --
↓
neu.spoon!(ノイスプーン):この日は休みだった・・・。
↓
Shimba' Cafe:札幌のフォーラムで知り合った方に教えてもらったカフェ。
↓
アスペルジュ:結婚式後に妻+妻の両親で旅行した際に行こうと思っていたけど行けなかったレストラン。
富良野の宿に泊まり、朝10時ぐらいに出発。『北の国から'95 秘密』で純とシュウが人に知られたくない過去について心の内を話した「北時計」という喫茶店があったのですが、2010年に閉店して、現在はボランティアによって運営されている「あかなら」を訪問。僕たちが2009年に訪れたときは「北時計」でしたが、「あかなら」になって店内の雰囲気も少し変わったようでした。ただ、流れる時間のゆっくりさは変わっていなかった気がしてなんかほっとしました。
あかならの外観
あかならの次はおなじみ「五郎の石の家」を訪問。見物客用の駐車場にレンタカーを停めて石の家に向かう途中、近くを流れる沢の石の上にヘビが!実は嫁さんヘビが生理的に苦手で、見るだけで身の毛もよだつほど。見ないようにして離れました。でも後から思い返すとヘビはのーんびりした様子で、石の上で身体をのばしてひなたぼっこしてたように思います。残念ながら写真には収められていませんが、嫁さんいわく「世の中あんなヘビばっかりだったらこんなに怖がるようにはなってなかったと思う」。石の家は、前回訪問時よりも草が伸び放題、羊もいなくてちょっとさびしかったですが、相変わらずすばらしい家。30分ぐらい何をするでもなく滞在しましたが、その間なぜか「スズメバチに刺されたらいやだ」とか「いま熊が出たら死ぬな」などと考えていました。自然の中に立ってみるとそんなこと考えるもんなんですかねぇ。
五郎の石の家
「五郎の生き方 今こそ」と新聞の切り抜きが貼ってありました
「拾ってきた家」は石の家から車で5分ぐらい。すべて廃材などを再利用して作った住宅が立ち並び、今後の僕ら夫婦の生活にはとても参考になります。
純と結の家 ※テレビでは登場していません
雪子おばさんの家。一人なのに広い!
それから富良野市内に戻り、北の国から資料館で三日月食堂のスタンプをもらう。「北の国から」の撮影場所でスタンプをもらえる場所があり、前回訪問時に三日月食堂以外は全てもらっていたのですが、今回、三日月食堂が閉店してしまっていて資料館でもらいました。
そこから札幌のフォーラムで知り合った方の絵が飾ってある「neu.spoon!(ノイスプーン)」という中富良野にあるお店を目指して出発。カーナビと地図でようやく見つけましたが、この日はお休みでした。。
その後は6月5日の宿泊先となっている旭川へ向かって寄り道する感じで再出発。途中、またも札幌のフォーラムで知り合った方に嫁さんが教えてもらった「Shimba' Cafe」というカフェに立ち寄ってひと息。間取りから建物の感じまでとても落ち着く、それでいておしゃれなお店でした。どこかおばあちゃんの家のような錯覚を覚えました。
Shimba' Cafe
この日の夕食は、美瑛にあるレストラン「アスペルジュ」で、美瑛の食材で作ったコースを堪能。実は今回、妻が「おしごと9年半おつかれディナー」としてごちそうしてくれました。「前に行けなかったから行こうよ」的なノリだったのですが、なんとびっくり。ありがとう。これからもよろしく。
嫁さんからのメッセージ
夫
PR
2012
June 04
June 04
6月4日の経路
きたキッチン:北海道産の厳選食品を売るお店。4日間の旅路の食糧(+おみやげ)を調達。
↓
札幌農学校第2農場:100年ぐらい前にクラーク博士が作った酪農の模範的施設。
↓
森彦:木造民家を再生して作ったおしゃれカフェ。
↓
聖ミカエル教会:アントニン・レーモンド氏設計による木造建築の教会。
↓
高城商店:木造の古い商店。看板や壁がいちいち風情のある感じ。
↓
旧北海湯:高城商店の近くにある古い建造物。
北海道大学のキャンパス内にある札幌農学校第2農場では牛舎など、建物の美しさを堪能。今後の家作りの参考にと、木の壁や窓のアップなど変な写真も撮りました。あと、北海道での酪農の歴史を読むと、なぜか僕は先人たちの偉大さよりも牛や馬たちを自分たちの都合で遠いところから連れてきて狭いところに閉じ込めていることが可哀想だと思ってしまいました。とはいえ、僕たちは酪農や畜産の恩恵にあずかっておいしいものを食べているわけだし。。食べ物を無駄にしないようにしようと改めて思いました。

札幌農学校第二農場 模範家畜房
森彦さんではおいしい水出しコーヒーをいただきました。この頃、古い木造民家っていいなと常々思っていたのですが、そんな思いにぴったりの感じ。僕の場合、子どもの頃目黒にあったおじいちゃん、おばあちゃんの家が古い木造で、その郷愁に浸れる感じがいいと思っているのかもしれません。

森彦
次に訪れた聖ミカエル教会については、うちはキリスト教ではないですが中を拝見させていただきました。木の梁が見えるようになっていて、「こんなふうに木を組むんだ」と感心しました。パンフレットに建物の図面が描いてあったのでもらってきました。今後の生活で何か参考になるかも。(キリスト教信者になるって意味ではありません)

聖ミカエル教会 外観
その後、高城商店、旧北海湯を見学して、遠路富良野の宿へ。遠路といっても2時間ぐらいで着きましたが。古い建造物は今後志す空き家再生の参考にと思ってこの後も何軒か見ます。

高城商店 外壁の一部

旧北海湯 外観
夫
きたキッチン:北海道産の厳選食品を売るお店。4日間の旅路の食糧(+おみやげ)を調達。
↓
札幌農学校第2農場:100年ぐらい前にクラーク博士が作った酪農の模範的施設。
↓
森彦:木造民家を再生して作ったおしゃれカフェ。
↓
聖ミカエル教会:アントニン・レーモンド氏設計による木造建築の教会。
↓
高城商店:木造の古い商店。看板や壁がいちいち風情のある感じ。
↓
旧北海湯:高城商店の近くにある古い建造物。
北海道大学のキャンパス内にある札幌農学校第2農場では牛舎など、建物の美しさを堪能。今後の家作りの参考にと、木の壁や窓のアップなど変な写真も撮りました。あと、北海道での酪農の歴史を読むと、なぜか僕は先人たちの偉大さよりも牛や馬たちを自分たちの都合で遠いところから連れてきて狭いところに閉じ込めていることが可哀想だと思ってしまいました。とはいえ、僕たちは酪農や畜産の恩恵にあずかっておいしいものを食べているわけだし。。食べ物を無駄にしないようにしようと改めて思いました。
札幌農学校第二農場 模範家畜房
森彦さんではおいしい水出しコーヒーをいただきました。この頃、古い木造民家っていいなと常々思っていたのですが、そんな思いにぴったりの感じ。僕の場合、子どもの頃目黒にあったおじいちゃん、おばあちゃんの家が古い木造で、その郷愁に浸れる感じがいいと思っているのかもしれません。
森彦
次に訪れた聖ミカエル教会については、うちはキリスト教ではないですが中を拝見させていただきました。木の梁が見えるようになっていて、「こんなふうに木を組むんだ」と感心しました。パンフレットに建物の図面が描いてあったのでもらってきました。今後の生活で何か参考になるかも。(キリスト教信者になるって意味ではありません)
聖ミカエル教会 外観
その後、高城商店、旧北海湯を見学して、遠路富良野の宿へ。遠路といっても2時間ぐらいで着きましたが。古い建造物は今後志す空き家再生の参考にと思ってこの後も何軒か見ます。
高城商店 外壁の一部
旧北海湯 外観
夫
2012
June 03
June 03
震災後の京都の流れから考えると、今回西村さんと皆川さんに同時に会ったことが自分にとって重要なものごとのつながりを意識させてくれる契機になったことは間違いないと思います。
それもそうだし、他の話し手の方々からも重要な考え方のヒントを得ることができたと思います。全員の話を聞いたうえで意識しながら生きていきたい思ったことをまとめてみると、お金がどれくらい儲かるかということだけが最重要なのではないということ、周りの人や自分が個々に持っている得意分野や特性をできるだけ切り捨てずに活かしてやっていくこと、自分や自分たちができることの範囲を見極めながらやっていくことです。
僕としてはどれも当たり前に誰もがやっていくべきことのように感じていますが、同時に、実現し続けていくことを忘れがちなことなんだと思います。
以下、今後の自分への備忘録も兼ねてそれぞれの話について感じたことを書いておきます。
ブーランジェリー・ジンの神さん夫妻の話では、奥さんが「たくさん稼がなくてもいいんです」とおっしゃっていたのが特に共感できました。また、西村さんとのやりとりの流れで「自分がこれからやろうとしていることの結果は特に気にしなかった?」→「やる前から結果分かるんですかね」というのが印象的でした。端的に自分たちの今後とつながるところでは、開店までのエピソードで空き家探しから土地探しにシフトして自分でガレージキットを組み立てるところが参考になりました。
福森伸さんはいわゆる障害者支援施設「しょうぶ学園」を運営している方。「障害者」という特別な種類の人間として接するのではなく「こういう特徴を持った人間」として普通にコミュニケーションするという考え方がよいと思いました。とは言え現実としてはいくつも問題を抱えている話もされていて、日本の社会が多様な個別の特徴を切り捨てながら発展を遂げてきたことの功罪を考えさせられました。
建築家をはじめ様々な仕事をされている中村好文さんは、「身の丈を超えないこと」を大切にして生きていることが話の内容や雰囲気から伝わってきました。これから空き家再生を志す僕としては好文さんの建築に対する考え方などを今後学びたいと同時に、生き方もぜひ参考にさせていただきたいと思っています。(好文さんの本をとりあえず1冊買って本人にサインをもらった。かなり安直ですが…)
エフスタイルの星野さん、五十嵐さんは、商品づくりにおいて自分たちが学んだデザインだけを絶対視するようなことはなく、工場や職人さんとじっくり話し合うことを重視している。僕としては、当たり前にやっていきたいけど現実にはなかなかできないあり方だと理解してます。星野さんの言葉「素直なものに戻していく作業」というのはピンときました。
奈良県にある「くるみの木」の石村由起子さんの話は、僕は個人的に「不意に大きな決断をしてしまったエピソード」というふうに捉えていて、この度自分がした「移住→DIY生活」というのも同じレベルの大きな決断だと思っています。なので、とても他人ごとに思えず聞いていました。そして「由起子さんがいなくなった後はどうする」との問いに対する答え、結論として「その時に残っていた人で考えてほしい」という感じですが、僕も同じ意見です。いなくなった後は、基本的に自分の力が及ばないですし、その時のことを考えるのは、言ってみれば「身の丈」に合わないことなんじゃないかと思います。
夫
それもそうだし、他の話し手の方々からも重要な考え方のヒントを得ることができたと思います。全員の話を聞いたうえで意識しながら生きていきたい思ったことをまとめてみると、お金がどれくらい儲かるかということだけが最重要なのではないということ、周りの人や自分が個々に持っている得意分野や特性をできるだけ切り捨てずに活かしてやっていくこと、自分や自分たちができることの範囲を見極めながらやっていくことです。
僕としてはどれも当たり前に誰もがやっていくべきことのように感じていますが、同時に、実現し続けていくことを忘れがちなことなんだと思います。
以下、今後の自分への備忘録も兼ねてそれぞれの話について感じたことを書いておきます。
ブーランジェリー・ジンの神さん夫妻の話では、奥さんが「たくさん稼がなくてもいいんです」とおっしゃっていたのが特に共感できました。また、西村さんとのやりとりの流れで「自分がこれからやろうとしていることの結果は特に気にしなかった?」→「やる前から結果分かるんですかね」というのが印象的でした。端的に自分たちの今後とつながるところでは、開店までのエピソードで空き家探しから土地探しにシフトして自分でガレージキットを組み立てるところが参考になりました。
福森伸さんはいわゆる障害者支援施設「しょうぶ学園」を運営している方。「障害者」という特別な種類の人間として接するのではなく「こういう特徴を持った人間」として普通にコミュニケーションするという考え方がよいと思いました。とは言え現実としてはいくつも問題を抱えている話もされていて、日本の社会が多様な個別の特徴を切り捨てながら発展を遂げてきたことの功罪を考えさせられました。
建築家をはじめ様々な仕事をされている中村好文さんは、「身の丈を超えないこと」を大切にして生きていることが話の内容や雰囲気から伝わってきました。これから空き家再生を志す僕としては好文さんの建築に対する考え方などを今後学びたいと同時に、生き方もぜひ参考にさせていただきたいと思っています。(好文さんの本をとりあえず1冊買って本人にサインをもらった。かなり安直ですが…)
エフスタイルの星野さん、五十嵐さんは、商品づくりにおいて自分たちが学んだデザインだけを絶対視するようなことはなく、工場や職人さんとじっくり話し合うことを重視している。僕としては、当たり前にやっていきたいけど現実にはなかなかできないあり方だと理解してます。星野さんの言葉「素直なものに戻していく作業」というのはピンときました。
奈良県にある「くるみの木」の石村由起子さんの話は、僕は個人的に「不意に大きな決断をしてしまったエピソード」というふうに捉えていて、この度自分がした「移住→DIY生活」というのも同じレベルの大きな決断だと思っています。なので、とても他人ごとに思えず聞いていました。そして「由起子さんがいなくなった後はどうする」との問いに対する答え、結論として「その時に残っていた人で考えてほしい」という感じですが、僕も同じ意見です。いなくなった後は、基本的に自分の力が及ばないですし、その時のことを考えるのは、言ってみれば「身の丈」に合わないことなんじゃないかと思います。
夫
2012
June 02
June 02
「自分の仕事を考える2日間」充実した2日間でした。
まずは主催者で進行役の西村さんに感謝です。昨年3月の震災後しばらく滞在した京都で西村さんの本に出会ってから頭の中でふつふつとしていた思いを、ようやく外の世界に出せた気がします。
また、京都滞在中にミナ・ペルホネンのショップでたまたまお会いした皆川明さんにも再び会うことができ感激しました。
今回のフォーラムでこの2人に会えたことは、どこか京都で考えきれなかったことの続きをさせてもらっているようでした。
フォーラムの進め方が面白くて、偉い先生からありがたいお話をお聞きしてその後少し質疑応答というスタイルではなく、話し手以外の人間どうしでも話し合う時間が設けられるようになっていて、常に当事者意識を持って参加できる仕組みでした。もちろん西村さんによる進行ありきな気はしますが。
それから、今回妙にがんばってしまった出来事として、皆川さんに東京スカイツリーのユニフォーム受注について質問したくだりをご報告します。僕はスカイツリーが大量生産・大量消費を象徴する建造物のような気がしていてあまり好きではなかったので、正直「どーなの?」と思っていた気持ちを伝えてみたのです。図々しくも、どういう経緯や思いがあってユニフォームを受注することにしたのかと。約300人の聴衆の前ということもあり超ドキドキしました。
皆川さんは丁寧に答えてくださいました。まず、スカイツリーに対する印象として僕と同じような大量生産・大量消費の象徴というような考えには思い至っていなかったとのお言葉。僕が勝手に思っていただけだから特に皆川さんがそこに思い至る必要はなかったのですが…。すいません
そして、国内で生産することを受注の条件としたこと、それを多くの人が訪れる場所にユニフォームとして提供できることをプラスに考えていること、またTシャツなどのグッズはスカイツリー周辺の工場で生産しているため、それが地元産業の向上につながると考えていることなどをご説明いただきました。
妻やその友人たちが憧れるファッションブランド『ミナ・ペルホネン』。僕が質問する前、皆川さんは生地の織り方などベースとなる部分のクオリティに、表に出る柄のデザイン図案などいわば空想による産物を丁寧に乗せていくことを大事にしていると語っていました。
使う人の満足度を考える際、多くの人は市場が求めるものをリサーチすることにとらわれてしまう傾向にあると思いますが、皆川さんが重視しているのはむしろ自らの哲学とも呼べる作り方へのこだわり。自己満足だけで商売は成り立ちませんが、「自分が満足できない状態で商品を世に出しちゃダメ」という思いにはすごく共感できるし、それだからこそ魅力あるモノを提供し続けられるのだと思います。
夫
まずは主催者で進行役の西村さんに感謝です。昨年3月の震災後しばらく滞在した京都で西村さんの本に出会ってから頭の中でふつふつとしていた思いを、ようやく外の世界に出せた気がします。
また、京都滞在中にミナ・ペルホネンのショップでたまたまお会いした皆川明さんにも再び会うことができ感激しました。
今回のフォーラムでこの2人に会えたことは、どこか京都で考えきれなかったことの続きをさせてもらっているようでした。
フォーラムの進め方が面白くて、偉い先生からありがたいお話をお聞きしてその後少し質疑応答というスタイルではなく、話し手以外の人間どうしでも話し合う時間が設けられるようになっていて、常に当事者意識を持って参加できる仕組みでした。もちろん西村さんによる進行ありきな気はしますが。
それから、今回妙にがんばってしまった出来事として、皆川さんに東京スカイツリーのユニフォーム受注について質問したくだりをご報告します。僕はスカイツリーが大量生産・大量消費を象徴する建造物のような気がしていてあまり好きではなかったので、正直「どーなの?」と思っていた気持ちを伝えてみたのです。図々しくも、どういう経緯や思いがあってユニフォームを受注することにしたのかと。約300人の聴衆の前ということもあり超ドキドキしました。
皆川さんは丁寧に答えてくださいました。まず、スカイツリーに対する印象として僕と同じような大量生産・大量消費の象徴というような考えには思い至っていなかったとのお言葉。僕が勝手に思っていただけだから特に皆川さんがそこに思い至る必要はなかったのですが…。すいません
そして、国内で生産することを受注の条件としたこと、それを多くの人が訪れる場所にユニフォームとして提供できることをプラスに考えていること、またTシャツなどのグッズはスカイツリー周辺の工場で生産しているため、それが地元産業の向上につながると考えていることなどをご説明いただきました。
妻やその友人たちが憧れるファッションブランド『ミナ・ペルホネン』。僕が質問する前、皆川さんは生地の織り方などベースとなる部分のクオリティに、表に出る柄のデザイン図案などいわば空想による産物を丁寧に乗せていくことを大事にしていると語っていました。
使う人の満足度を考える際、多くの人は市場が求めるものをリサーチすることにとらわれてしまう傾向にあると思いますが、皆川さんが重視しているのはむしろ自らの哲学とも呼べる作り方へのこだわり。自己満足だけで商売は成り立ちませんが、「自分が満足できない状態で商品を世に出しちゃダメ」という思いにはすごく共感できるし、それだからこそ魅力あるモノを提供し続けられるのだと思います。
夫
2012
June 02
June 02
「自分の仕事を考える2日間」というフォーラムに参加するため札幌にやってきました。昨日送別会でもらった本も一緒に。

自分の仕事を考える2日間 in 札幌
http://www.kitakara.org/content.php?id=6406
本は心やさしい昨日までの仕事でのチームメンバーが送ってくれました。今日読みはじめたばかりなので、後日読み終わったら読書感想文を書きます。
フォーラムは、今日は前夜ワークショップで、「好きなことを仕事にする」ということについて知らない人とグループを作って話し合うという内容。進行はデザイナーで働き方研究家の西村佳哲(よしあき)さん。
西村さんは他人に対して「好きなことで仕事されてるんですね」というようなことを言うのには抵抗があるそうで、「好き」が仕事になっていることが必ずしもよいことではないのではないか、というような投げかけを前提としてグループで話し合いました。
僕としては、確かに「好き」だけでやってる仕事がうまくいくとは思わないし、成功のための絶対条件として「好き」がなくてはいけないとも思わない。
でも「好き」(享受して楽しむのではなく能動的に関わりたいこと)で突っ走るような仕事がないというのもつまらないと思ったり。まだ答えにはたどり着いてないですね。
明日、明後日も引き続きフォーラムです。今後のヒントが見つかるといいなあ。
夫
自分の仕事を考える2日間 in 札幌
http://www.kitakara.org/content.php?id=6406
本は心やさしい昨日までの仕事でのチームメンバーが送ってくれました。今日読みはじめたばかりなので、後日読み終わったら読書感想文を書きます。
フォーラムは、今日は前夜ワークショップで、「好きなことを仕事にする」ということについて知らない人とグループを作って話し合うという内容。進行はデザイナーで働き方研究家の西村佳哲(よしあき)さん。
西村さんは他人に対して「好きなことで仕事されてるんですね」というようなことを言うのには抵抗があるそうで、「好き」が仕事になっていることが必ずしもよいことではないのではないか、というような投げかけを前提としてグループで話し合いました。
僕としては、確かに「好き」だけでやってる仕事がうまくいくとは思わないし、成功のための絶対条件として「好き」がなくてはいけないとも思わない。
でも「好き」(享受して楽しむのではなく能動的に関わりたいこと)で突っ走るような仕事がないというのもつまらないと思ったり。まだ答えにはたどり着いてないですね。
明日、明後日も引き続きフォーラムです。今後のヒントが見つかるといいなあ。
夫
